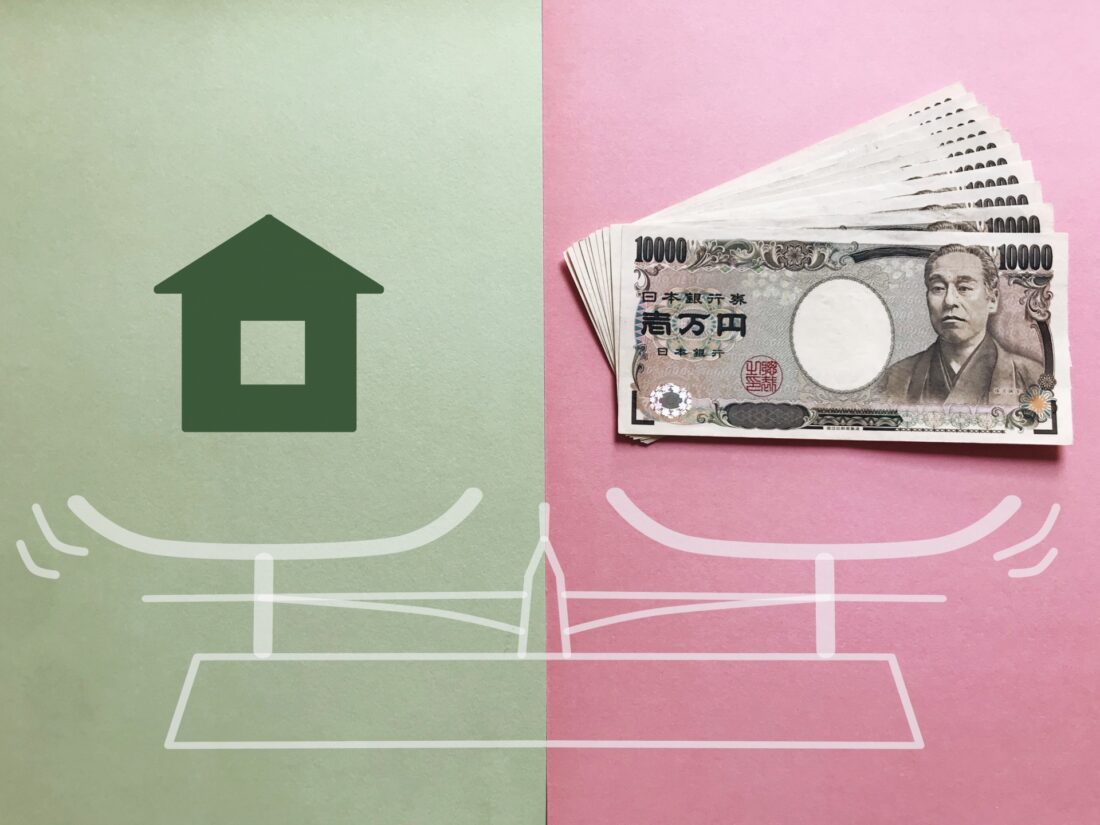目次
はじめに
注文住宅を購入するにあたっては、多くの方が住宅ローンを利用しますが、どのようにして選ぶのがいいか悩む方も多いと思います。というのも、住宅ローンには事務手数料や保証料、返済方法など、全体の金額に影響してくるチェックポイントが非常に多いからです。
今回は、金利の種類を紹介するとともに、0.1%の差がどのくらい返済額に違いをもたらすのかをシミュレーションしてみました。住宅ローンで損をしないために、これから住宅購入を検討している方にチェックしていただきたいと思います。
金利とは?
まず最初に、金利とはどのようなものかについて説明したいと思います。金利とは、お金の貸し借りで借り手が貸し手に対し、借入金額に上乗せして支払う対価の割合です。利息とは、借りた人から見て「借りたお金」の対価を指します。金利には年利、月利、日歩(ひぶ)という3つの表示パターンがあって、住宅ローンの場合ですと、借りたお金に対して1年間に支払う利息の割合として「年利」で表示されることになっています。
住宅ローンの特徴は、金融機関が定めている「基準金利(店頭金利)」と、基準金利から引き下げ金利が行われた「借入金利(適用金利)」がある点です。引き下げ金利とは、設定した条件を満たした場合に基準金利から引かれる金利のことで、金融機関により優遇金利とも呼ばれます。使用目的が限られていることや住宅が担保になることから、カードローンや自動車ローンよりも金利が低いことも特徴といえるでしょう。なお、これらの基準金利や引き下げ金利は、それぞれの金融機関の基準で決められているので、各金融機関で異なることを知っておきましょう。
出典:モゲチェック
金利にも種類がある

・変動金利型
変動金利型とは、一定期間で適用される金利が見直される住宅ローンです。変動金利型のメリットは、固定金利型と比較すると借入時の金利が低いことにあります。しかし、金利が変動するため借入時には総返済額が見通せないことや、返済期間中に金利が上がった場合には、予定していたよりも返済額が上がってしまう可能性があるというデメリットもあります。変動金利型で適用される金利は通常半年ごとに見直されますが、適用金利が変わっても月々の返済額は5年間変わりません。5年後の返済額は、その時点での元金残高や残りの返済期間、金利により再度計算されて決まります。なお返済額は、直前の返済額の1.25倍までという決まりがあるため、適用金利が大幅にアップした場合でも、返済額が極端に大きくは上がらない仕組みになっています。
・固定金利期間選択型
固定金利期間選択型は、選択した期間中だけ固定金利になるタイプの住宅ローンです。固定金利には3年、5年、10年、20年などの期間があり、短いほど金利も低くなります。固定金利期間を10年で選択した場合、契約当初の金利が10年間続き、11年目に再度固定金利期間を選択します。11年目から適用される金利は、固定金利期間を選択した時点のものになる場合と、残りの返済期間が変動型になるタイプの場合があります。
・全期間固定金利型(フラット35)
全期間固定金利型は、借入時の金利が借入期間ずっと変わらず、毎回の返済額や総返済額が借入時に決定されます。代表的なものが、民間金融機関が住宅金融支援機構と提携して取り扱っている「フラット35」という住宅ローンです。全期間固定金利型のメリットは資金計画を立てやすいことや、金利上昇に伴う返済額の増加を心配する必要がない点です。ただし、デメリットとして変動金利や固定金利期間選択型と比較して、金利は最も高くなります。さらに市場金利が下がっても金利はずっと一定であるため、経済情勢によっては変動金利で住宅ローンを組んだ場合よりも総返済額が多くなることもあります。
出典:伊予銀行
金利0.1%の違いで月々の返済額はどのくらい変わる?
それでは、金利が0.1%変わるとどの程度返済額に影響を与えるのかを見てみましょう。次の表は、借入金額別に金利差0.1%ごとの総返済額にどれだけ違いが出るかをまとめたものです。(借入期間は35年)
<総返済額>
借入額 金利0.40% 金利0.50% 金利0.60% 金利0.70%
3,000万円 3,215万円 3,271万円 3,327万円 3,383万円
4,000万円 4,287万円 4,361万円 4,436万円 4,511万円
5,000万円 5,359万円 5,451万円 5,545万円 5,639万円
6,000万円 6,431万円 6,542万円 6,654万円 6,767万円
7,000万円 7,503万円 7,632万円 7,762万円 7,895万円
例えば3,000万円の住宅ローンを借りた場合、金利が0.1%違うと、月々の返済額の差はおよそ1,300円です。月に1,300円の差なら大きな差ではないように感じる方もいるかもしれませんが、住宅ローンは返済が長期間にわたるため、35年にもなると、560,000円も差が生じます。金利が0.5%も変わると、約300万円もの違いになることから、わずかな金利の差が総返済額に大きく影響することが分かります。さらに借入金額が増えるほどその差は大きくなり、借入額が5,000万円の場合は0.1%の金利差で、月々の返済額がおよそ2,200円、総返済額が92万円の差となります。
住宅ローンの商品によっては、保証料や事務手数料を無料にしたり、付帯サービスがついていたりすることも多いのですが、上記のように金利0.1%の違いによる金額差が大きいため、その差が簡単に埋められてしまうケースが多いのです。そのため住宅ローンを選ぶにあたっては、まずは金利を一番重要視することが大切だと言えるでしょう。
出典:ダイヤモンド不動産研究所
4.平均所得から考える住宅ローン
それでは最後に、平均所得や注文住宅の平均価格から、住宅ローンについて考えてみましょう。
住宅金融支援機構が2023年度に実施した、フラット35利用者を対象とした調査によると、世帯年収の平均は660.5万円で、1ヵ月に換算すると約55万円という結果でした。
注文住宅(土地代は含まない)の所要資金の平均3,863万円のうち、平均3,040万円の融資を受けている結果が得られています。3,040万円の住宅ローンを金利1.0%で35年組んだ場合、月々の返済額は8.6万円で、年間の返済額は103.2万円です。
ここで、収入の中の返済金額の比率を割り出すために「年間のローン返済額÷年収×100」で計算してみると、収入における返済金額の比率は約15.6%であることが分かります。
一方、土地付注文住宅の所要資金の平均は4,903万円であり、そのうち平均で4,171万円の融資を受けているという結果が出ています。4,171万円の住宅ローンを金利1.0%で35年組んだとすると、月々の返済額は11.8万円で、年間の返済額は141.6万円です。先ほど使用した返済比率の計算式に年間返済額と平均世帯年収660.5万円を当てはめますと、返済比率は約21.4%であることが分かります。
返済比率は20~25%程度までが理想といわれているため、上記の平均金額の例でいうと金利1.0%ならば土地代の有無に関係なく無理のない返済ができているといえそうです。
ただし、住宅ローンだけではなく、子どもの教育費や思いがけない医療費、マイカー費用など、生活していくにはさまざまなお金がかかるものです。できるだけ無理のない返済プランを立てるためには、金利の低い商品を選択するのが賢明といえます。
出典:住宅金融支援機構 2023 年度 フラット35利用者調査
まとめ
いかがでしたでしょうか。
家づくりをするときは資金計画など、さまざまな悩みが生じるでしょう。特に住宅ローンについては、長期間支払い続けるものですので、生活費や教育費など、ライフプランをしっかりと立てて住宅ローンを選ぶことが大切です。住宅ローンの選び方に関する相談も承っていますので、これから注文住宅のご購入を検討されている方は、ぜひ万代ホームでご相談ください。