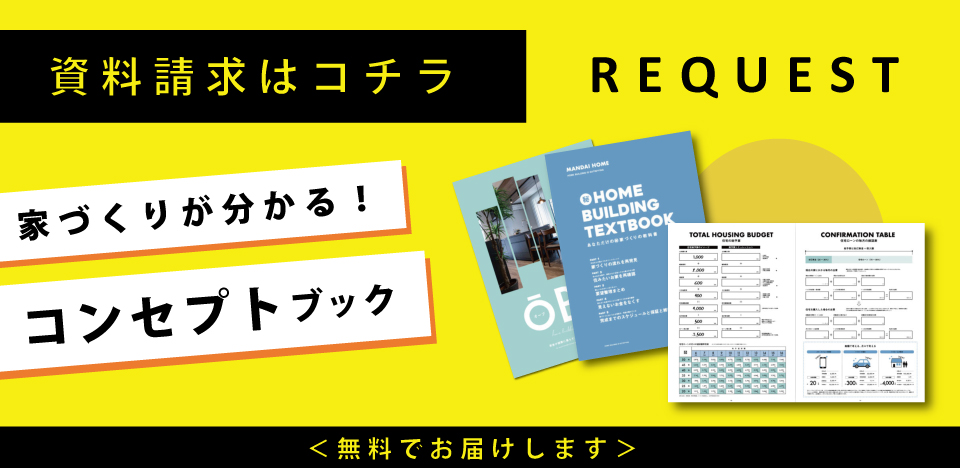目次
はじめに
住宅は人生でもっとも高い買い物の一つであり、ほとんどの人が購入時に住宅ローンを利用します。住宅を購入するにあたり、「住宅購入にかかる所要資金の目安がどれくらいか」「どれくらいの価格帯の物件を視野に入れておけばよいか」「月々の返済額はどれくらいが妥当か」など、悩む人も多いのではないでしょうか。
この記事では、住宅購入にかかる所要資金の目安や、住宅ローンの借入額・月々の返済額の目安などの考え方について解説していきます。
1.住宅ローンの支払額には2種類ある
まずこのテーマを考えるにあたって、予め知っておかなければならないことがあります。
それは、住宅ローン支払額には、「毎月の返済額」と「総支払額」の2種類があるということです。
1つ目は毎月の返済額です。毎月の返済額が多すぎると、家計が圧迫され、返済が滞ることにもなりかねません。滞納を続けると住宅の権利を失う場合もあるため、毎月の返済額は無理のない金額に設定することが大切です。
2つ目は総費用(総支払額)です。総費用(総支払額)とは住宅ローンを借りたことで発生する支払額の合計額です。
例えば、住宅ローンとして3,000万円を借りた場合、金融機関に返済する金額は3,000万円ではありません。
金利や借入期間に応じた利息、借りる際の手数料、保証料、抵当権を設定する登記には登録免許税も必要です。また、抵当権設定登記の手続きを司法書士に依頼する場合は司法書士報酬などもかかり、これらを含めた費用の合計額を総支払額といいます。
長い目でみると大きく差が出る場合もあるので、まずはこの2つがあることを知っておきましょう。
出典:auじぶん銀行
2世帯年収と住宅購入の資金の目安
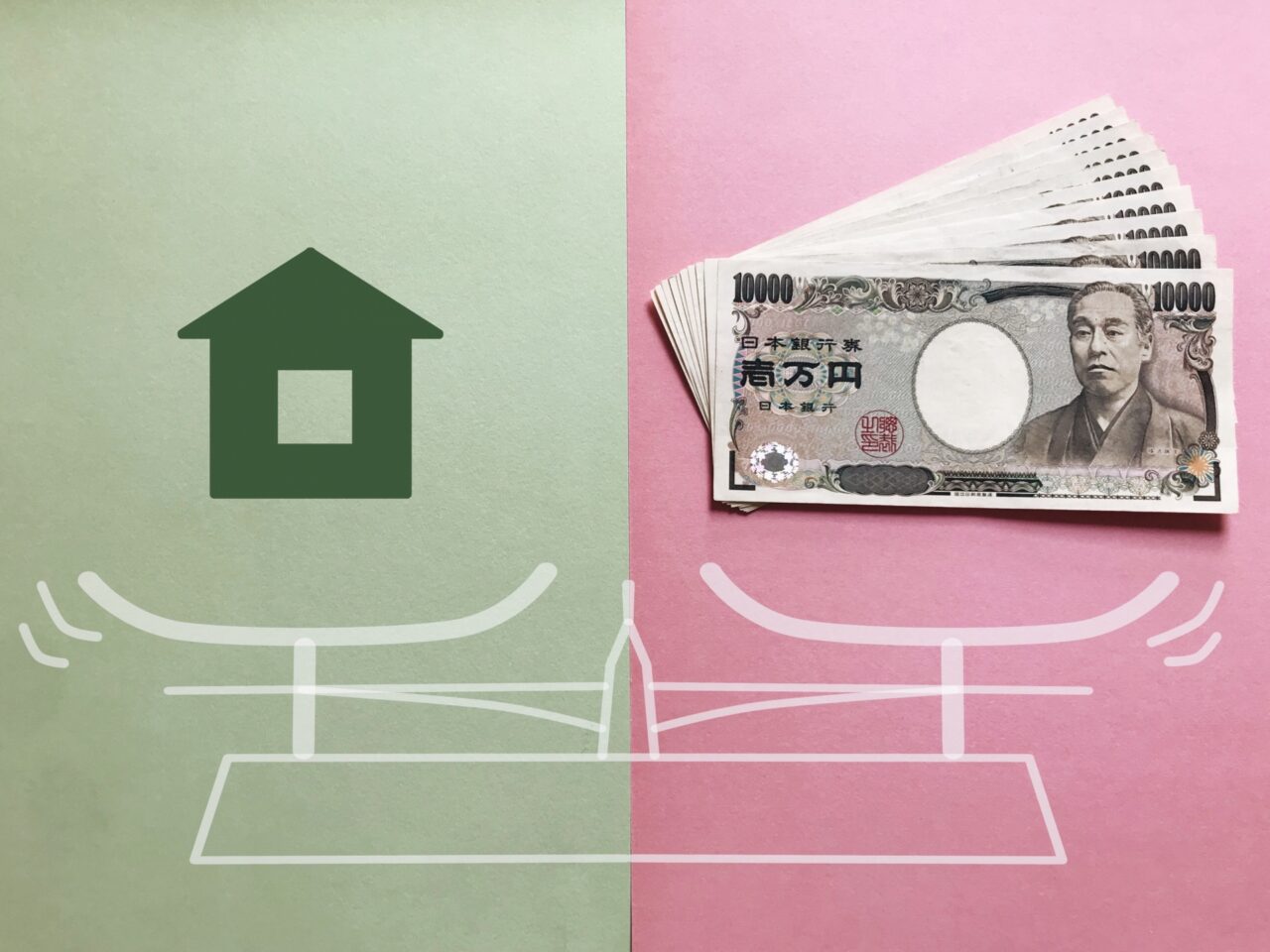
全国平均でみると2024年は、注文住宅の場合は所要資金3936万円・年収倍率6.9倍、土地付き注文住宅の場合で所要資金5007万円・年収倍率7.5倍となっています。
年収倍率とは住宅ローンを組む際の審査基準の一つで、「購入価格÷年収」で算出される、物件の購入価格が年収の何倍にあたるかを示す指標です。金融機関は融資可能額を判断する際、年収倍率を参考にします。一般的には、住宅ローンは年収の5〜7倍、最高でも8〜10倍程度が目安とされますが、住宅の種類や地域の地価、自己資金の有無などによって異なります。詳しくは、過去のコラム「熊本市で注文住宅にかかる費用相場は?予算別にできる住宅の特徴も紹介」もご参照いただければと思います。
なお、一番多い年収が4~500万円であることを踏まえ、世帯年収450万円の方が土地付き注文住宅を購入するケースを例にあげますと、この場合の年収倍率は
450×7.5=3375万円
となり、ここから頭金の金額を引いたものが住宅ローンの金額となります。
また、毎年無理なく返せる住宅ローンの返済額は、一般的に年収の20%~30%と言われていますので、この例の場合の妥当な返済額は年間90~135万円ということになります。
年収から年間の返済可能額を計算し、返済期間を考慮して、借入額を検討しましょう。
参考コラム:熊本市で注文住宅にかかる費用相場は?予算別にできる住宅の特徴も紹介
3. 借入額別シミュレーション(35年返済・元利均等・ボーナス払いなし)
次に、返済のシミュレーションをみていきましょう。
ここでは「金利1.0%」「金利1.5%」の2パターンで、借入額3,000万・4,000万・5,000万円の月々返済額をシミュレーションしました。
借入額
| 借入額 | 金利 | 月々返済額 | 総返済額 |
| 3,000万円 | 年1.0% | 約84,686円 | 約3,557万円 |
| 3,000万円 | 年1.5% | 約91,855円 | 約3,858万円 |
| 4,000万円 | 年1.0% | 約112,914円 | 約4,742万円 |
| 4,000万円 | 年1.5% | 約122,474円 | 約5,144万円 |
| 5,000万円 | 年1.0% | 約141,143円 | 約5,928万円 |
| 5,000万円 | 年1.5% | 約153,092円 | 約6,429万円 |
毎月の返済額だけ見ると「少しの差」に見えますが、35年続けば総額で数百万円の差となります。これは無視できません。
4. 住宅ローンの返済方式 ― 元利均等返済と元金均等返済
返済額を計算するときに大切なのが「返済方式」です。
元利均等返済
元金と利息を合わせた返済額が毎月ほぼ一定。家計管理がしやすく、初めて住宅ローンを組む人に選ばれることが多い方式です。ただし、最初のうちは利息の割合が多く、元金がなかなか減りません。
元金均等返済
毎月返す元金部分は一定で、利息分が徐々に減るため返済総額は少なくて済みます。ただし最初の数年は返済額が高くなるので、家計に余裕のある世帯向きです。
返済方式の比較例
仮に3,000万円を35年で借りた場合、金利1.0%では元利均等なら月々約8.4万円ですが、元金均等では初期に約9.6万円となり、その後少しずつ減っていきます。総返済額は元金均等のほうが少なく済む一方、初期負担は大きくなります。この差を理解して選ぶことが重要です。
金利タイプの違い ― 変動金利と固定金利、そしてフラット35
住宅ローンの返済額は金利によって大きく変わります。
変動金利
半年ごとに見直され、金利が下がれば返済額も減ります。現在は低金利が続いているため人気ですが、将来上がったときには返済額が膨らむリスクがあります。実際に1990年代には金利が5%を超えた時期もあり、その頃に借りた世帯は大きな負担を抱えました。もし現在1.0%で借りていたローンが2.0%に上がったとすると、3,000万円借入で月々約8.4万円→約9.9万円へと1.5万円増え、年間では18万円、35年で600万円以上の差となります。
固定金利
返済中ずっと金利が変わらない安心感があります。金利は変動型より高めですが、長期的な計画を立てやすいのがメリットです。教育費や老後資金の見通しを立てたい家庭には向いています。
2025年8月時点では、変動金利が0.525%前後、固定金利(フラット35)は1.870%程度と差があります。
フラット35
国が支援する固定金利型ローン。最長35年間、返済額が一定です。利用には住宅の床面積や技術基準を満たす必要がありますが、省エネ性能や耐震性能が高い住宅を建てれば金利優遇が受けられます。団体信用生命保険(団信)も付帯でき、病気や死亡時のリスクにも備えられる安心感があります。中古住宅でも利用できるため、リノベーションを考えている方にも活用されています。
借入額に応じた世帯年収とは
それでは、これまでにご紹介した情報を踏まえ、ここまで借入金額のベースとして考えてきた3000万円・4000万円・5000万円の金額別に、現実的に借入をするのが妥当な世帯年収の目安について考察します。
3000万円
金利1.0%で、返済期間35年の場合、月々の返済額は約8.5万円です。年間支払金額は102万円。妥当な年収倍率が5~7倍と考えると約430~600万円となり、500万円前後の世帯が該当します。
4000万円
金利1.0%、35年返済で、月々の返済額は約11.3万円です。年間支払金額は135.6万円。妥当な年収倍率が5~7倍と考えると約570~800万円となり、700万円前後の世帯が該当します。
5000万円
金利1.0%、35年返済で、月々の返済額は約14.1万円です。年間支払金額は169.2万円。妥当な年収倍率が5~7倍と考えると約710~1000万円の世帯が該当します。
住宅ローンを考えるときに大切なこと
住宅ローンは教育費や老後資金、万が一の医療費や介護費用とならび、人生全体の大きなライフプランにかかわる支出の一部です。希望するマイホームを買うために借入れしたい金額がある一方、借りすぎてしまうと、必要な貯蓄ができない、返済が厳しいといった状況になりかねませんので、ローン返済だけを基準に考えるのではなく、ライフイベントに合わせた長期的なプランニングが不可欠です。無理をすることなくご家庭にあった住宅ローンを組むことが大切です。
まとめ
いかがでしたか。
毎月の返済額は「借入額」「金利」「返済方式」で決まります。
今回は一般的なデータをもとに妥当と思われる世帯年収までを割り出してみましたが、もちろん各家庭の家族構成や教育方針、職業や自動車の所有の有無によってもこのあたりが変化します。
大切なのは、人生全体のライフプランを見据えた住宅ローン選びをすることです。個別の資金相談にも対応しておりますので、気になった方はぜひ万代ホームにご相談ください。